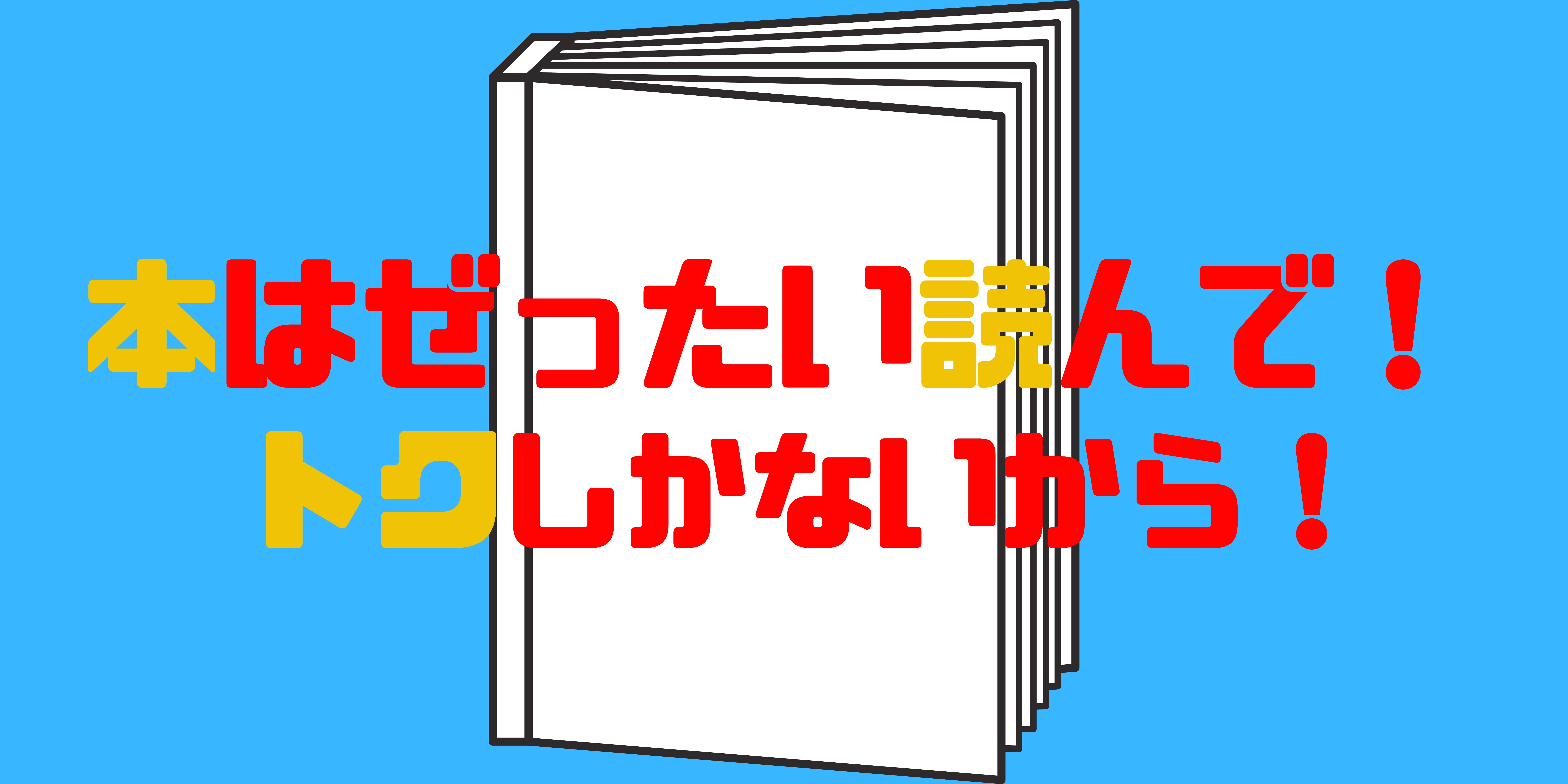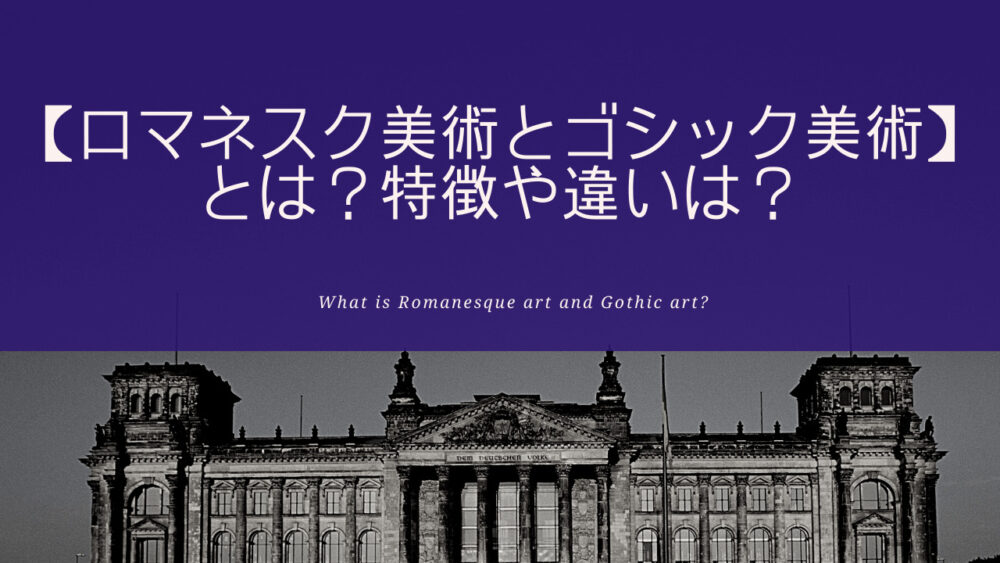
【ロマネスク美術とゴシック美術】違いは?5分で分る!簡単にスピード解説!

mars
どうもこんにちはマルスです。
みなさんは西洋美術の歴史に興味はありますか?
美術館などで美術品を見て何やら考えている人を見た事がないでし
あの人達を見て何を考えているんだろう、
歴史や何故作られたのか、
今回はそんな西洋美術の10世紀〜14世紀頃の「
その前の時代の「初期キリスト教美術」が気になる人は、こちらの記事を読んでね。
この記事の目次
【ヨーロッパ全域に広まった!2大美術様式】
西ローマ帝国の滅亡後、ヨーロッパではキリスト教公認、
俗に「中世」と言われ、美術を含むあらゆる文化活動が、
10世紀頃には、神聖ローマ皇帝とローマ教皇の二重権力による、
この影響を受け、
この様式を「ロマネスク(ローマ風)様式」と呼ばれ、
その後生まれるのが「ゴシック様式」です。
ゴシック様式とは、ルネサンスの文化人が前時代の様式を、
ゴシック様式は12世紀〜14世紀頃まで続きます。
【信仰心を高める美術が発展する】
ロマネスク様式もゴシック様式も、キリスト教美術が全てで、
しかしその中でも特殊な工芸品もあり、

「聖女フォワの人型聖遺物容器」985年頃 サント・フォワ聖堂、コンク(フランス)
3世紀の禁教時代に布教して、
これ自体が崇拝の対象となる特殊な工芸品。
【ミサ(聖餐式)のためのロマネスク教会】
教会では主にミサ(聖餐式)が行われました。
聖餐式とはキリストが最後の晩餐で弟子たちに行った奇跡を、
聖餐式では、聖別されたパンとワインが使われます。
初期キリスト教時代の西ヨーロッパでは、

「サント・マドレーヌ大聖堂」1138年 ヴェズレー(フランス)
ロマネスク様式の教会は、きれいな半円形のヴォールト(天井)
代わりに柱頭や扉口の上部の、
【柱頭とタンパン!彫刻家の凄腕】
人々は煉獄での浄化期間を短縮する目的で、西ヨーロッパ全土で「
そのため巡礼路の各地に、祈りのための教会ができていき、
ロマネスク教会の入口、
教会内部には、ほとんど装飾はされず、

「最後の審判」サント・フォワ聖堂正面扉ティンパヌムより 12世紀 サント・フォワ修道院、コンク(フランス)
中央に審判を下す神、キリストがいる。右手を上げ、

「エジプトへの逃避」サン・ブノワ・シュル・
向かって右が、ヘデロ王による嬰児虐殺から逃れるため、
左が、ドラゴンを退治する大天使ミカエル。
【広く、高いゴシック教会】
経済活動が活発になり、
もともと皇帝と教皇の傘下にいた商人たちが、
いくつかの教区のまとまりである司教区があり、
この大聖堂は街のシンボルとなっていき、
12世紀半頃〜14世紀まで主要な建築様式となった「
そのおかげで荷重を増す事ができ、側壁面に、

「ミラノ大聖堂の内部」1386年 ミラノ
広さは信徒の増加のためで、高さは天に少しでも近づくため。
【満を持して登場!ステンドグラス】
ゴシック教会は荷重を柱に集中させるので側壁面にガラス窓を設置
電灯がないこの時代、教会内部を明るく照らすガラス窓は、
聖職者が多人数で、大きな紙を見る事ができるようになったので、

「サント・シャペル内部、聖書諸場面の連作ステンドグラス」
マリア伝やキリスト伝の諸場面が描かれています。

「美しき絵ガラスの聖母」12世紀後半 シャルトル大聖堂(フランス)
ゴシック教会建築の傑作、
【修道院で生まれた超絶高価!写本挿絵】
カトリック教会の管轄下にある修道院は、
修道院は、世俗の生活から離れ、
キリスト教中世では、印刷技術がまだ無いため、
それらに装飾的な縁取りや挿絵を加えたものを「装飾写本」
羊や子牛の皮「ベラム」で出来た紙に鉛丹(赤色系顔料)
ベラムは1頭からごくわずかしかとれず、
修道院内部での集団生活は、独自の文化を生み今までにない「

ファクンドゥス「海と地から現れる怪獣」「
黙示録の第12章に登場する、
【まとめ】
どうでしたか?
この中世の時代にヨーロッパ全域に広まった「ロマネスク」と「
こうして美術の時代背景が分かると、凄く面白いですよね。
今回の記事がみなさんの役に立つと、凄く嬉しいです。
ではまた別の記事で。

mars
またねー
参考資料